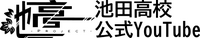ぶどうから広がる科学の世界~施設見学編~|1年次・科学と人間生活
10月20日 午前
9月下旬には町長による講話、10月上旬にはブドウ畑での収穫体験を実施しました。
これまでの活動の詳細は以下からご覧いただけます。
・池田町のアイデンティティを学ぶ「ワイン学」|1年次・科学と人間生活(講話)
・今年もぶどう収穫を行いました|科学と人間生活・1年次(ブドウ収穫)
今回は第3回目の見学として、池田町のワインについて、歴史・製造工程・地理などを学ぶ時間となりました。
今回も、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所 製造課長の東様よりご説明いただきました。
お忙しい中、誠にありがとうございました。
赤ワインの仕込み工程
まずは赤ワインの仕込みの様子を見学しました。
除梗(じょこう)破砕機で枝と実を分け、液体がタンクに流れ込んでいきます。
これがワインの原料となり、町民用のロゼワインやブランデーに加工されるそうです。
▲枝ごとブドウが入れられ除梗破砕機で仕分けされます

▲液体が大量に出てきました
ワインとブランデーの歴史
東様からは、池田町におけるワイン・ブランデー造りの背景について、以下のような説明がありました。
1960年代の寒冷な気候ではぶどうが完熟せず、酸味が強くワインには不向きでしたが、ブランデーには適していました。
フランス・ボルドーの例を参考に、池田町でも酸っぱいぶどうを活用したブランデー造りが始まりました。
ロゼワインのように発酵させた後、蒸留を繰り返してアルコール度数を高め、熟成年数に応じてVS、VSOP、XOなどのランクに分類されます。
以前はXOを出すのに15年以上かかっていましたが、現在は8年程度で可能になっています。
2014年のNHKドラマ「マッサン」以降、蒸留酒ブームが再燃し、ウイスキーとともにブランデーも注目されるようになりました。
1993年以降途絶えていた製造が2015年から再開され、現在は熟成年数を表示した商品が市場に出ています。
ワイン造りの歴史と地域の工夫を知る貴重な機会となりました。
スパークリングワインの製法と設備
池田町は、日本で初めてシャンパーニュ製法を導入した地域とのことです。
▲普段立ち入ることのできない場所に入って説明を受けることができました。
工場内の様子と工程
工場に入る前のタンクには、ほぼ完成されたワインが入っています。
樽は長時間かけて乾燥させて作られます。
瓶は新品でも洗浄して使用します。
▶コルクダストや漏れの確認をする機会です
ワインの貯蔵と管理
1969年からのワインが貯蔵されており、アルファベットで種類を分類しています。
▲こちらも一般の方は入ることのできない施設
▲利別小学校から寄贈された棚も活用
▲1年次生の誕生年のワインを発見!
タンク内は澱と液体に分かれ、週2回継ぎ足しながら空気に触れないよう満量で管理(15度・湿度70%)します。
地理と品種改良の学び
池田町の地理について説明を受けました。
土壌の違いがぶどうの味に影響することや、品種改良の工夫についても学びました。

生徒代表の謝辞
最後に、生徒代表の松村さんより謝辞が述べられました。
見学を通してワインがとても身近に感じられるようになり、特にスパークリングワインの作り方など、これまで知らなかったことを学べてとても興味が湧きました。
北海道に来て半年ほどの自分にとって、今回の体験は貴重で楽しいものでした。
2時間にわたる丁寧な説明と案内、ありがとうございました。
来週以降、今回の学びをもとに学校でレポートを作成する予定です。