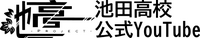配慮をするということ|3年次選択・形態別介護技術
配慮って?
今回は、障害福祉サービスの押さえておくべき基礎知識を身につけることと、配慮とは何かを考える疑似体験の二本立て。
講師の小川先生から、支援には様々な形態があることを教わりました。
まずは知ることからはじめましょうという時間。スライドを使いながらゆっくり丁寧に話を進める小川先生。コミュニケーションでも大切な〈間・ま〉を、生徒と共有しているような時間でした。
また「聴こえない人の気持ちを体験するんじゃなくて、自分が介助者になったときに相手にどんな配慮ができるかを体験してほしい」と。
聴覚障害の疑似体験。
イヤーマフを使ったグループワークでは、聞こえない人がいる場面を作ってみんなで雑談。その過程で、聞こえない人を仲間はずれにしないためにはどうすればいいのか、配慮の大切さを体験しました。場が温まってきたところで、ジェスチャーゲームと伝言ゲームへ……。
授業を終えた悩み多き生徒たち
「人に伝えるって難しいよね」
「あーだよね、こーだよねって言う話を聞くと、色んな考え方があるよなぁって」
「コミュニケーションって、そういうもんだよね」
なんとなく自分だけの考えだけじゃうまくいかないよねってことがわかった、今回の授業なのでした。
#イヤフォンを付けて大音量で音楽を鳴らしてイヤーマフも付ける。みんな、なに話してるの?

#ジェスチャーゲームにも挑戦!笑いをとっているわけじゃないけど笑われる。
これも生活の中での配慮を考えるきっかけになるかも。

#伝言ゲーム、伝わらない!

※イヤーマフとは
耳全体を覆うタイプの防音保護具です。イヤーマフは、もともと工事現場や飛行場、射撃、モータースポーツなどの騒音が大きい場所で、それらの仕事に携わる人の耳を守る道具として使用されてきました。近年では、防音効果が高いことから、一般の方にも広まってきており、特に大きな音が苦手な、聴覚過敏がある方にとって、音から自分を守るツールの一つとなっています。