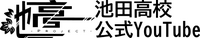ワインの製造工程を学びました|科学と人間生活・1年次
10月17日
池田高校のワイン授業3回目。
今回も多くの方に学びの機会を与えていただいたことを感謝申し上げます。
1回目:町長によるワイン学の講演
2回目:ブドウ畑で収穫体験
3回目:製造工程の見学
ということで、本日は、ワイン城とブドウ・ブドウ酒研究所を見学させていただきました。
前回同様、池田町ブドウ・ブドウ酒研究所の製造課長である東さんにご説明いただきます。
到着早々、駆け足で工場へ!
収穫したブドウを今まさに破砕したりしているところでした。
ちょっと離れて作業を見守ります。
#ロゼワインの仕込み中。軽くブドウを潰して、果汁だけをとっています。
ブドウ模型を使いながらわかりやすく説明してくださいます。
搾りかすとなった皮や種は、飼料になりほとんど捨てることがありません。
授業でも学んでいるSDGsですね。
#次にこの場所を通ったときには作業が終わり、搾りかすが置かれていました。
次に、スパークリングワインの製造方法について説明を受けました。
フランスのシャンパーニュ地方で作られる「シャンパン」と同じ製法である「瓶内二次発酵法」を採用しています。
当時フランスに行って勉強し、苦節9年、やっと商品化できたそうです。

#瓶内二次発酵の時にできる「オリ」の取り方の説明を受けています
#スパークリングワインのコルクは、実は赤白ワインと同じストレート型。3ヶ月ほどたつとおなじみのマッシュルーム型になるそうです。
続いて、ワイン工場へ。
あと1週間ほどすれば、ここでも実際に充填作業が始まるそうです。

ワイン城へ。
#今日も良いお天気です。良い景色。
地下熟成室です。ここでは樽熟成をしています。現在168樽あり、池田中学校の生徒たちが収穫し成人式の時に渡されるワインもここで熟成されているそうです。

#使い終わった樽は、ウィスキーやさんやサウナ利用する方などに良いお値段で売れるそうですよ。
ブランデー蒸留室へ。
なぜ池田町でブランデーが作られたのか歴史が語られます。
寒すぎて良いブドウが採れない地方だからこそ、ブランデーを作りはじめた。しかし、蒸留酒ブームがくるまでなかなか売れず苦しい時代も長く続きました。
池田町のワインの歴史は寒さと品種改良とそれに立ち向かう人々の苦労の上に成り立っていることが伝わってきます。
品種改良の歴史をお聞きしました。

こちら、気づかない方もいるのではないでしょうか。ワイン城の正面にあるモニュメント。
山幸の木を研究するため、生きた木を抜いて作ったそうです。根がものすごく長いのがわかります。これでも保管の関係上少し切ったそうです。
#清見地区と千代田地区の土壌の違いと赤ワイン白ワインの関係も説明されました。
いつかワインを飲み、味の違いがわかるようになるとこの説明もしっくりくるでしょうね
さて、ここからはスペシャルタイム!
ご厚意により、とても貴重な場所を見学させていただきました!
旧ブドウ・ブドウ酒研究所です。
狭い階段から地下に降りていきます。
「カブトムシ飼ってるにおいがする!」と叫ぶ池高生。
こちらには、オールドビンテージのワインが保管されています。
1970年のセイオロサムの赤ワインなど、高校生にとっては、両親や祖父母の生まれた年のものになるでしょうか。

別の部屋には「課税庫」がありました。ここは貸しワインセラーになります。
年中一定の温度湿度に保たれた地下で、十勝ワインを保管することができます。
月500円、年間6,000円だそうですよ。
こちらには、ブランデーやワインがありました。
私達の身長よりも大きい加水樽もあります。

池高生からも積極的な質問がありました。「この樽のものを売ったらいくらくらいになりますか?」「先ほど、ブランデーを作る過程で水蒸気を冷やすので無色透明の液体と説明がありましたが、どんな過程によって色がつくのですか?」など、鋭い質問も。

#「最新の品種改良ではどんなブドウを作っているのですか?」
普段見られない特別な場所を、池田町の歴史とともにたっぷり教えてくださいました。
池高生ならではスペシャル講義をしていただき感謝いたします。
来週はまとめの授業。どんな知識を得たり、気づきを得たりしたのでしょうか。