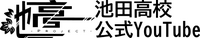池田町の課題に向き合う・キャンプファイヤー|2年次選択・ライフデザイン
11月某日。役場の林務課の方々にご協力いただき、池田町の炭窯でキャンプファイヤーをしました。
ライフデザインの授業で、池田町の放置される木のことを知った生徒が、その木でキャンプファイヤーができないかな?と思い、今日は実際にやってみました。
#これは運び込まれている木
太めの木で井桁型に組み、火をつけます。
風がある日だったのもあり、人の背丈ほどの炎が上がります!

#薪をどんどん追加すると、さらに火力があがります!
#風向きで火の向きが変わり、ちょっと逃げたくなる場面も。
周りで見守る大人も、「思ったより迫力あるね…」「こんなにうまくいくとは思わなかった」とあとずさり。
試してみようか、と準備していたシャボン玉液が凍ってしまうほどの寒い日。
火って暖かいなぁとしみじみ感じます。

暖かいお茶を飲んでみたら、それはもう美味しかった。

さてさて本番。ただ楽しむためにこれだけの人にご協力いただいたわけじゃない。
外部講師でお世話になっている中村さんに問いかけられます。
キャンプファイヤーは楽しかった?どんな時にやりたい?
このイベントにいくらまでなら払える?一緒にやるならどんなイベントが考えられる?
お金をとるとしたら、その原資はどこからくるかな?

キャンプファイヤーをするのに、いくらかかりますか?
その内訳は何になりますか?個人だと難しいのですか?
場所はどういう名目なら借りられるのですか?
疑問に思ったことを、林務課の方々に聞きます。

#生徒はビジネスの話しをしていましたが…
「どうして土台の木は燃えないのか?」
「煙が臭いが、良い匂いにすることはできる?」
「火の色って変えられるものですか?」など私は自然現象に関わる質問をしておりました‥
あたりが暗くなり、用意していた薪も少なくなりました。

#終わりかけの火がとてもキレイです。
カメラの腕と言葉にするセンスがなく、これは是非体感していただきたいところ。
きっちり消火活動をして終了。
机上ではなく、実際に体験すること。
これは得難い経験です。
皆さんにお伝えしたいのはもちろん、池田高校の生徒にも伝えたいです。