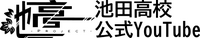2024年9月の記事一覧
夏休みの池高生、まつりを盛り上げる!(課外活動)
今回は、夏休み中の池高性の活動を紹介します。
池田町の子どもたちの居場所〈放課後サロンエルム〉は週一回の開催だけど、池田小学校の子どもたちがわんさかやってきます。池高生たちも放課後の時間を使って、子どもたちに呼ばれて毎週のように遊んでいます。
8月10日は、子どもも池高生も夏休み真っ盛り。
〈サロンエルムの夏まつり〉がありました。
的あて・輪投げ
お菓子釣り
水風船
スタンプラリー……
池高生たちは、前日の準備から当日の役割まで、子どもたちの笑顔のためにアイデアを出し合って楽しんでいたけど、暑かった!がんばった
最後はみんなでスイカ割り。水分もたっぷりとって、思い出もたっぷり詰まった夏まつりになりました。池田の夏のヒトコマでした。
ちびっこと池高生。お姉さん、お兄さんになってました
みんなのキッチンのカレーを「いただきます!」
まつり一番の大仕事〈スイカ割り〉でも池高生大活躍!
幼稚園の防災訓練(2年次・保育基礎)
9月13日(金) 午前
「いけだ こうこうまで あるこーう!」という授業がありました。
幼稚園の子どもと先生たちに、保育基礎を学んでいる池高生8名が、防災の話をしました。
自己紹介は子どもたちからのリクエスト。
「好きな食べ物」と「好きな電車」。電車!? りんご、桃、お寿司、甘いもの…… 黄色い電車、青い電車、毎日乗っている電車、などなど。
お話が始まると、学校では見られない池高生の隠れた才能?隠していた魅力?に、「はい、はい、はい!」と、子どもたちもノリノリ!
川の近くにある幼稚園の避難所が、丘の上にある池田高校なんです。歩くのは、1.4キロメートルくらい。
子どもたちは車に気をつけて、「みぎみて、ひだりみて、もういっかい みぎをみて、てをあげて」。高校生と手をつないで真剣に歩きました。
子どもが好きだったり関わったことがなかったり、いろんな気持ちを持って彼らを安全に助け出した池高生たち。お兄さんとお姉さんの手を小さい手で握り返していた子どもたちが印象的でした。
「あまいものがすきです」「ちょこれーと!」「けーき!」。
ドキドキしながらお話しました。
「にげる とき おやつは もって いっていい?」「だめぇ!」
正解は……「◯まる!」
ふたりで一緒に手をつないで。さぁ しゅっぱ〜つ!
「とおいーねぇ」みんな がんばれ〜!
学校の中を探検して、遊んで、食べて、ばいばい!
今年は池高生が実行委員長!「10/27(日)ハロウィンイベント2024」|課外活動
2023年に、旧利別小学校跡地活用を模索するため、町民の有志の方たちが開催してくださった、ハロウィンパーティー。子どもたちが50人以上も集まる大好評のイベントとなりました。
今年は、企画・準備から池田高校生が関わりたい!と、池田高校で実行委員会が立ち上がりました!
開催日は10月27日(日)13:00−14:30@旧利別小学校
準備状況も随時発信していきます!
#経緯や準備について、昨年代表を務めた八木さんにお話を伺います
#差し入れまでいただき、やる気Max!楽しいイベントにするぜ!
防災避難訓練を実施しました
9月17日 午後
『地震に伴う火災発生による避難』を想定して、防災避難訓練を実施しました。
学校で避難訓練を行う目的は、
・授業中に火災が起こった場合の避難方法と避難経路の確認する
・避難行動を体験することで自らの防災、減災意識を高める
です。
避難の様子は撮影できませんでしたが、生徒の皆さんは先生方の指示に従い、迅速に行動していました。
また、先生方にとっても、学校現場で災害が発生した場合の対応を確認する貴重な時間となりました。
避難後は、『消火訓練』と『脱出シュートによる降下訓練』です。
消火訓練です。消防署の方から消火に関する重要なアドバイスをいただきました。
・消火器は使い切る
・火の根元を狙う
・火元の遠くから箒で履くように
・姿勢を低くする
・自分の避難経路を背にして消火活動を行う
脱出シュート訓練です。3階図書室から避難しました。
最後に、消防署の村木様から講評をいただきました。
お話の中に、
◎訓練を自分事として捉えることで命を守ることにつながる。
◎落ち着いて行動する。考えて行動する。
とありました。
災害はいつ起こるかわかりません。
今日の訓練を活かし、災害関連の報道を目にした際には、『自分だったらどうすべきか?』と考えることで、減災につながると感じます。
池田消防署の皆様、本日はお忙しい中、ご指導いただき誠にありがとうございました。
みなさんがいま、自由に生活することは幸せなことですよ(2年次・総合探究)
9月4日 午後
池田高校では、2年次の見学旅行で広島を訪ねます。
それに合わせて、戦争体験者講話の授業がありました。
玉置さん(御年88歳の在校生のお祖母様)は、戦時中の小学3年生だった大阪でのこと、空襲のこと、疎開のこと、いつもおなかがすいていたこと、亡くなった友だちのこと、大人になって気がついたこと、そして戦争は絶対にしてはいけないということを話してくれました。
「社会に目を向けて下さい」
「疲弊していく池田町を見て下さい」
それを意識するために、政治に関心を持ちなさい、選挙で表現しなさい、と。
そして、タイトルにある言葉を池高生たちに伝えてくれました。

池高生からは……
「分からないから、知らないからで終わらせてはいけない」
「繋いでいくことが大切」と、玉置さんへの御礼の言葉がありました。
この日は朝のラジオで大貫妙子さん(ミュージシャン)が特攻隊の話をしていました。
「父は特攻隊が美化されることを、常に危惧していました」。
帰宅してラジオをつけると、『あたらしいげんばく展』(AR:渋谷のスクランブル交差点に原爆が落ちたら)を紹介していました。
偶然にしてはと思い、今日はなんの日だろうと調べてみると……
日露講和条約(ポーツマス条約)が調印された日でした。
玉置さんは最後に、
德元穂菜さん(当時小学2年生)沖縄全戦没者追悼式・平和の詩『こわいをしって、へいわがわかった』
を紹介してくれました。