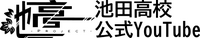池高日誌
防災避難訓練を実施しました
9月17日 午後
『地震に伴う火災発生による避難』を想定して、防災避難訓練を実施しました。
学校で避難訓練を行う目的は、
・授業中に火災が起こった場合の避難方法と避難経路の確認する
・避難行動を体験することで自らの防災、減災意識を高める
です。
避難の様子は撮影できませんでしたが、生徒の皆さんは先生方の指示に従い、迅速に行動していました。
また、先生方にとっても、学校現場で災害が発生した場合の対応を確認する貴重な時間となりました。
避難後は、『消火訓練』と『脱出シュートによる降下訓練』です。
消火訓練です。消防署の方から消火に関する重要なアドバイスをいただきました。
・消火器は使い切る
・火の根元を狙う
・火元の遠くから箒で履くように
・姿勢を低くする
・自分の避難経路を背にして消火活動を行う
脱出シュート訓練です。3階図書室から避難しました。
最後に、消防署の村木様から講評をいただきました。
お話の中に、
◎訓練を自分事として捉えることで命を守ることにつながる。
◎落ち着いて行動する。考えて行動する。
とありました。
災害はいつ起こるかわかりません。
今日の訓練を活かし、災害関連の報道を目にした際には、『自分だったらどうすべきか?』と考えることで、減災につながると感じます。
池田消防署の皆様、本日はお忙しい中、ご指導いただき誠にありがとうございました。
みなさんがいま、自由に生活することは幸せなことですよ(2年次・総合探究)
9月4日 午後
池田高校では、2年次の見学旅行で広島を訪ねます。
それに合わせて、戦争体験者講話の授業がありました。
玉置さん(御年88歳の在校生のお祖母様)は、戦時中の小学3年生だった大阪でのこと、空襲のこと、疎開のこと、いつもおなかがすいていたこと、亡くなった友だちのこと、大人になって気がついたこと、そして戦争は絶対にしてはいけないということを話してくれました。
「社会に目を向けて下さい」
「疲弊していく池田町を見て下さい」
それを意識するために、政治に関心を持ちなさい、選挙で表現しなさい、と。
そして、タイトルにある言葉を池高生たちに伝えてくれました。

池高生からは……
「分からないから、知らないからで終わらせてはいけない」
「繋いでいくことが大切」と、玉置さんへの御礼の言葉がありました。
この日は朝のラジオで大貫妙子さん(ミュージシャン)が特攻隊の話をしていました。
「父は特攻隊が美化されることを、常に危惧していました」。
帰宅してラジオをつけると、『あたらしいげんばく展』(AR:渋谷のスクランブル交差点に原爆が落ちたら)を紹介していました。
偶然にしてはと思い、今日はなんの日だろうと調べてみると……
日露講和条約(ポーツマス条約)が調印された日でした。
玉置さんは最後に、
德元穂菜さん(当時小学2年生)沖縄全戦没者追悼式・平和の詩『こわいをしって、へいわがわかった』
を紹介してくれました。
北大からの留学生をお出迎え準備|選択授業・2年次英語コミュニケーションⅡ
9月下旬に、Hokkaido Study Abroad Programで北大で学んでいる留学生が、2名池田高校に来てくれることになりました。
今日の授業は、池田駅についてから、学校までエスコートする時の下見です。
実際のルートを歩きながら、どんなものが目につくか、説明できるかをチェックしながら歩きます。
あれ、リスって英語で何だっけ…?
先生「squirrelですよ〜」
(写真右:今日は実際にリスに出会えました♪オレンジが可愛かったなー)
この木は何かわかりますか?あれ?日本語でも言えない…?
身近にあるものって、意識していないと結構説明できないものですね。
途中で二手にルートを別れて散策。時間がどのくらいかかるかや、見えるものを確認します。
あとで確認すると、Googleマップにものっていない、車輪のモニュメントなど、池田の歴史を含めて彼らが説明してくれました。さすがよく知ってる!
(前はここの池ぐるっと一周できたんだけどなぁ〜)
ワイン城の中も見学。貯蔵庫は温度や湿度、匂いも違うのを実感します。

(忘れないように写真も撮っています)
レストラン・カフェからの風景も確認
ここから見える景色、説明できるかな?
(筆者が異様に青春を感じた一枚。みんな何を見て、何を想っているのかなー)
どこで記念撮影をすると良いかもチェック。
今日の下見を元に、英語でどのように説明するか、次からの授業で準備します。
生きた英語を使うチャンス!実際、留学生がどのような反応をするかも楽しみですね。
若いうちに外へ出ろ♪(2年次・英語探究)
池高に着任してひと月、生徒と活動を始めて10日くらい。
高校魅力化推進員の〈amiちゃん〉が、英語探究という授業に登壇しました。
北海道の池田にやってくる前は、東京の大きい会社で働いていたり、海外で生活をしたり、あれしたりこれしたりと、池田にはなかなかいない経歴の持ち主だったりするんです。
ということで、ベトナムでの暮らしの一部を紹介してくれました。ワニとか犬とかパジャマとかドンとか、異文化理解の話を、全身を使って説明しています。
「ところ変われば……」という異文化との付き合い方、馴染み方、食べ方、受け止め方を生徒たちは学びました。表題の言葉は担当の先生の言葉。うん、旅をしよう!
仏教の国だけど、他国と違ってファンキーな仏像が多いんだって
ワニ、1万頭。落ちちゃダメなヤツ
食べ物好きのひとの写真
タワマン事情も日本とは違うんだって

生徒のみなさんにとって、異文化に触れる良い機会になりましたね。
授業することで学ぶ|池高3年次生が池小4年生に授業(課題研究の一環)
9月4日(水)じゅんの森にて、池田高校3年次生の2チームが考えた森林体験プログラムを実施しました。
この授業、いつもは一般社団法人 森の輪(もりのわ)の福家さん(元池田町地域おこし隊)が行う森の授業です。今回はその貴重なお時間をいただき、池田高校3年次生が探究の授業として、プログラムを考えました。
高校生チームは、夏休みから福家さんと一緒に森を下見したり、試作で小屋を作ったりと事前準備を行ってきました。
#夏休みの様子。役場の林業課の方々にもお世話になっております
そして迎えた当日!
池田小学校4年生の約30名がやってきました。
森の輪の福家さん、役場の林業課の皆さん、地域おこし協力隊、小学校の先生たちとたくさんの大人に見守られながら授業がスタート。
今回のプログラムは、
①基地をつくろう!
②白樺の間伐材キットで動物を作ろう!
の2つのコースがあります。
①基地を作ろう!は、アイヌの方が狩猟の時に使う仮小屋をモデルにしています。
3本の木に、笹をまとめたものをさしていき、雨風をしのぎます。
#笹(下草)を刈ることも森の保全活動につながると福家さんが教えてくれました。
②白樺の間伐材キットで動物を作ろう!は、最初に高校生が紙芝居でなぜ間伐材を使うのか物語にして説明。
次に森の中に入って、素材採取を行い、工作です。
小学生の想像力はすごい!想定外の素材の使い方をしていました。
最後に、小学生から感想とお礼の言葉。あっという間に過ぎていった60分でした。
授業が無事終わり、ホッと一息。森で記念撮影
地域の方と関わり、子どもたちと関わった高校生。
事前の準備や段取りの大変さ、意図をもった授業や当日の動き、子どもたちの反応が喜びになること…いろいろ学んだのではないでしょうか。
大人側の方がハラハラしていたかもしれません。
たくさん裏側から支えてくれた地域の皆様、ありがとうございます。
当日手伝ってくれた、大阪出身の地域おこし隊員が「都会ではできない貴重な経験。本当に羨ましいなー」としみじみ言っていました。本当にそう思います。
高校生たちの帰り道の背中が、一回り大きく見えました。